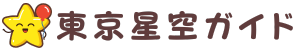空は毎日のように目にするものですが、「なぜ青いのか?」と問われると、意外と説明に悩む人も多いのではないでしょうか。
同様に、同じ空が夕方になると赤く染まるのはなぜなのか。
この記事では、空が青く見える仕組みや、夕焼けが赤く見える理由を解説します。
空が青く見えるのはなぜ?
太陽の光には“色”が含まれている
一見すると白く見える太陽の光ですが、実はその中にはさまざまな色の光が混ざり合っています。
これを証明するのが「虹」であり、雨上がりなどに虹が見えるのは、太陽の光が空気中の水滴にあたって赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の7色に分かれるからです。
つまり太陽の光は、もともと色の成分をたくさん含んだ光=白色光なのです。
また太陽光は、色によって「波長」という性質が異なっています。
赤い光は波長が長く、青や紫の光は波長が短いという特徴があり、この波長の違いが、空の色が青く見える理由につながっていきます。
青い光は大気で散らばりやすい
太陽光が地球の大気に入ると、光は空気中の分子(酸素や窒素)とぶつかり、四方八方に散らばります。
この現象は「レイリー散乱」と呼ばれ、波長の短い青い光ほど強く散乱される性質があります。
すると私たちの目には、あらゆる方向から青い光が届くことになり、空全体が青く見えるのです。
紫の光の方がさらに波長が短いのですが、人間の目は紫にはあまり敏感ではなく、また太陽光には紫が少なめなため、結果として空が青く見えるというわけです。
夕焼けが赤く見える理由は?

太陽が低いときは、光の通り道が長くなる
日中、太陽は頭の上から差し込んでくるため、光は大気を比較的短い距離で通過してきます。
しかし夕方になると、太陽は地平線近くに沈みかけ、私たちの目に届く光は厚く広がった大気の層を斜めに長く通過することになります。
このとき、短い波長の青や紫の光は、通過中にどんどん散乱し、ほとんど目に届かなくなります。
代わりに、波長が長くて散乱されにくい赤やオレンジの光だけが、私たちの元に残って届くのです。
赤く見えるのは“残った光”だから
つまり夕焼けの赤い色は、空が赤く染まったというよりも、青や緑などの光が散ってしまい、赤だけが残った結果にすぎません。
空の色は、光の何色が“届いたか”で決まっているため、夕方は自然と赤っぽく見えるのです。
また大気中に水蒸気や塵、微粒子が多い日には、さらに青い光の散乱が進んで赤さが増す傾向があり、火山の噴火や黄砂、PM2.5の影響などがあると、特に印象的な夕焼けが見られることがあります。
空の色でわかる大気の状態
空の色は単に青や赤で美しいだけでなく、大気の状態を知らせてくれるものでもあります。
実は、空の色合いによって空気が乾いているのか、湿っているのか、あるいは埃や汚れが多いのかを、ある程度読み取ることができるのです。
たとえば鮮やかな青空が広がる日は、空気中の水蒸気や微粒子が少なく、乾いた状態であることが多いです。
一方で白っぽく霞んだ空は、湿度が高かったり、微細な粒子が多く含まれている可能性を示しており、夏の蒸し暑い日や、黄砂・PM2.5が多い日の空に顕著です。
また夕焼けが赤く見えるのも、空気中の粒子の多さが関係しています。
火山の噴煙や森林火災などが起きた後は、光の散乱のしかたが変わり、普段以上に赤く濃い夕焼けが見られることもあるなど、空の色は見た目だけでなく、気象や環境の変化を感じ取る手がかりにもなるのです。
まとめ
空が青く見えるのは、太陽の光のうち、波長の短い青い光が大気によって強く散乱されるためです。
反対に、夕方には太陽の光が厚い大気を通ることで青い光が散らばり、残った赤やオレンジの光だけが届くため、夕焼けが赤く見えるようになります。
空をただ見るのではなく、「なぜこう見えるのか」と少しだけ立ち止まって考えることで、日常の景色がぐっと深く、面白く感じられるようになるはずです。