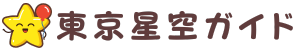戦国時代の武将と天体は、意外なほど深く結びついています。
たとえば農民の出身とも伝えられる木下小一郎(後の豊臣秀長)は、農事暦として太陽や月の動きを強く意識していたでしょう。戦国の世において、天体は戦の判断や生活の基準そのものでした。
そうした時代背景を思い浮かべると、武将たちが家紋や兜に天体を思わせる意匠を用いた理由も見えてきます。中でも誰もが思い出すのは、伊達政宗の三日月の前立てでしょう。
伊達政宗 ―― 月を身にまとう武将
伊達政宗と言えば、三日月の前立てです。隻眼の眼帯と組み合わさったその姿は、戦場にあっても強烈な印象を放ち、まさに伊達者と呼ぶにふさわしいものでした。
しかしこの三日月は、単なる奇抜な装飾ではありません。月は欠けては満ちる天体であり、再生や成長、そして時の循環の象徴です。
若くして当主となった政宗にとって、三日月は自分の立場を雄弁に語るデザインだったのでしょう。未完成であっても、これから満ちていく存在であることを示しています。
政宗は天体を信仰したのではなく、その意味を読み取り、自らの像として視覚化した武将だったと言えます。
上杉謙信 ―― 星を背負った越後の武将
伊達政宗が月を身にまとった武将だとすれば、上杉謙信は星と結びついた存在です。謙信は毘沙門天の化身と自らを称し、深く信仰していました。
この毘沙門天は、北斗七星信仰と結びつく軍神でもありました。そして北斗七星は、古くから天の秩序や帝王の権威と結びつけて考えられてきたのです。
謙信にとって星は、飾りではなく、戦う理由を裏づける信仰そのものでした。
月を個人の象徴として用いた政宗とは対照的に、謙信は星を通じて、自らを天の秩序に結びつけた武将だったのです。
軍師 ―― 天体を読む専門家たち
戦国時代において、天体の動きを読む役割を担ったのは、武将だけではありませんでした。軍師と呼ばれる存在の多くは、もともと陰陽道や占星術の知識を持つ人々だったのです。
山本勘助や太原雪斎といった名軍師は、吉凶や日取りを占い、天の意を読む役割も果たしていました。戦は天の流れに逆らっていないかどうかを測る行為でもあったのです。
武将たちは、「天を読む者」を側に置くことで、自らの決断を正当化していたのです。軍師は、現代の天文学者と同じような仕事をしていたのですね。
細川幽斎 ―― 星を「知」として扱った武将
細川幽斎は、戦国武将であると同時に、和歌や古典に通じた教養人でもありました。
家紋に用いられた九曜紋は、太陽と月、そして五つの肉眼で見える惑星から成る宇宙の体系を表すものです。さらにインド占星術で語られる二つの概念(ラーフとケートゥ)を加え、九つの丸として表されます。
当時は天王星と海王星の存在は知られていませんでした。しかし当時の知の体系において、天体の構成は九曜という形で整理されていたのです。
幽斎にとって星は、世界を理解するための知の枠組みでした。天体は信仰の対象ではなく、学ぶべき秩序だったのです。
毛利元就 ―― 星の「並び」を読む戦略家
毛利家の一文字三星紋は、「一」の文字の下に三つの星が配置されています。星の配置を読み、状況を見極める判断力を思わせるデザインです。
数と並びによって秩序を表すこの紋は、戦況を冷静に読み続けた毛利元就の姿と重なります。
さらに丸が三つあるため、毛利元就が息子たちに託した三矢の訓を連想させますよね。
ある日、元就が子供の隆元、元春、隆景を呼び寄せ、矢を折らせるエピソードです。実際はフィクションなのですが、毛利本家と吉川、小早川の分家が協力し合うことを諭しています。
まとめ ―― 天体は誰のためにあったのか
紹介した武将たちは、いずれも戦や政治と深い関わりを持ち、天体を象徴や思想として用いていました。
しかし当時の社会において、天体の動きと最も切実に向き合っていたのは、武将ではなく庶民だったのかもしれません。
豊臣秀長がそうであったように、多くの人々は月の満ち欠けや季節の星を農事暦として受け取り、日々の暮らしに生かしていました。
その実用的な天体観は形を変えながらも、今なお私たちの暦や行事の中に息づいています。戦国の空は、確かに現代へとつながっているのです。