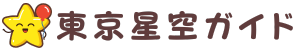年間を通して、最も美しい月は中秋の名月と言われています。たしかにこの夜の月はとても美しく魅力的です。十五夜お月さまと言えば、中秋の名月のことです。
日本人は中秋の名月が大好きで、丸いお団子を積み上げてお供えします。その横にはすすきを飾り、美しいお月さまを祝福します。いわゆる月見(観月)の行事ですね。
そして2025年の中秋の名月は10月6日です。
こんなに遅い中秋の名月?!
ところで、お月見と言えば9月の印象がありませんか?
国立天文台によると、1991年から2030年までの間で、中秋の名月が10月6日というのは最も遅い日付です。40年間で中秋の名月が10月になるのは8回あり、なかでも2006年と2025年だけが10月6日です。
参考:国立天文台の暦Wikiのページ
中秋の名月がこんなに遅いなんて、お月さまになにか異変でもあったのでしょうか?
そんなことはありません。これはひとえに旧暦の都合なのでご安心ください。お月見は旧暦を基準に考えます。
旧暦は陰暦(正確には太陰太陽暦)ともいい、月の満ち欠けを基準とする暦です。ですからお月さまが主役です。
旧暦の秋は7月、8月、9月で、それぞれ初秋、仲秋、晩秋とも呼ばれます。仲秋の真中の日は秋の真中ですね。よってこの日を「中秋」と呼びます。旧暦の8月15日が中秋です。
ですから8月15日の夜空に見える月が中秋の名月です。この夜は概ね満月であり空気も澄み、特に美しいとされています。
「月々に 月見る月は 多けれど 月見る月は この月の月」と詠まれるほどです。
中秋の名月が遅れた理由とは?
月の満ち欠けを基準に考える旧暦の1ヶ月は、概ね29日か30日です。12ヶ月では354日になり、太陽暦に比べて約11日少なくなります。
そのため実際の季節とは少しずつズレが生じ、およそ3年で太陽暦よりもほぼ1ヶ月分、足りなくなる計算です。
そこでズレがある程度まで大きくなり1ヶ月分溜まったら、まるまる1ヶ月加えて、調整します。かなり乱暴なやり方のようですが、これが閏月(うるうづき)の考え方です。
ですから旧暦では1年が12ヶ月になったり、13ヶ月になったりします。
閏月は調整用なので、どこに入れるかは決まっていません。一応ルールはありますが、不定期です。その閏月が2025年に入れられました。
太陽暦で2025年7月25日から8月22日までの29日間が旧暦の閏6月でした。このため旧暦では2025年は384日なのです。
この時期に閏6月が1ヶ月加わったため、中秋の名月も10月にずれ込んだのですね。
旧暦は楽しくて便利
旧暦を知っておくと、楽しくなります。特に天文ファンだと夜空に関係する話題が多いため楽しさ倍増です。
例えば七夕は、旧暦の7月7日ですからいつでも上弦の月です。七夕伝説では天の川が登場しますが、半月を船に見立てることもありました。
十五夜は満月ですが、旧暦の十五日の夜で、十三夜、十六夜(いざよい)も旧暦だとそのまんまの日付です。三日月が見られるのは、旧暦の毎月3日です。
旧暦の毎月1日は新月で、朔日(さくじつ、ついたち)とも呼ばれます。「ついたち」は「月立ち(つきたち)」から来ているそうで、月の始まりを意味します。
そもそも1月、2月、3月という言い方が、旧暦を基準に考えるとしっくりきますね。
歴史の出来事と夜空の関係
歴史に登場する日付は、もちろん旧暦で表記されています。
例えば本能寺の変が起こったのは6月2日の早暁です。新月になったばかりなので、明智光秀は闇夜の行軍だったはずです。気づかれにくい夜だったのですね。
また藤原道長の望月の宴は、10月16日に開催されており、その夜はほぼ満月だったことが、日付を見ただけでわかります。
旧暦でお月さまを眺めると趣が増しますよね。