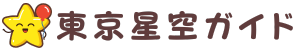荒川区最大の区立公園
荒川自然公園は、東京都水道局の「三河島水再生センター」の上に作られた人工地盤に設置された、荒川区立公園です。運営は、区から業務委託を受けた富士植木・施設管理サービス企業共同体が行っています。
北側地区、中央地区、南側地区の3つのエリアに分かれ、それぞれ「交通園と芝生」「運動と遊戯」「休養と散策」のエリアとなっています。6万平方メートルを超える広さは、荒川区立公園では最大の公園となり、新東京百景の1つにも選ばれています。
1974年に、テニスコートや野球場、プールといった運動施設や児童遊園コーナーがある現在の中央地区が「三河島処理場公苑」として開園。1979年には、白鳥の池や水辺広場、昆虫観察園などがある現在の南側地区が開園し、名称も公募により「荒川自然公園」となりました。
1996年には交通園や芝生広場「さんさん広場」などがある現在の北側地区が開園し、公園全体が完成しました。
園内は北側・中央地区と、南側地区に分かれており、それぞれで開園時間も異なっています。
自然や広場があり、天体観測の場にも
荒川自然公園は東側に隅田川が流れ、西側には都電荒川線が通り、周囲は住宅街となっています。そのため周囲には大きな高層ビルは存在しません。
また三河島水再生センターの上に作られたということで、公園には階段やスロープを登って入る必要があり、少し高い位置になっています。
こういった条件が、天体観測スポットとしてはメリットになります。
園内には北側地区のさんさん広場や、中央地区のふれあい健康広場といった大きな広場があり、南側地区は白鳥の池や水辺広場といった自然が広がるエリアとなっています。
天体観測をするにもこういった広場は周囲を見渡せやすく、場所の確保にも好都合です。
星空の学校〜École Étoile〜が定期的に観望会
荒川自然公園では、星空の学校〜École Étoile〜(エコエト)が定期的に星空観望会や天文イベントを実施しています。
星空の学校は、六本木天文クラブで行われた星空案内人養成講座の第1期生が実践の場として企画・運営を始めたものです。都会での星空の楽しみ方を発信しています。
交通園や自然観察の場も
荒川自然公園には、幼児~小学生を対象とした交通園もあります。小学生が対象となる自転車や、小学2年~6年生が対象の足踏み式ゴーカート、幼児向けの豆自転車や三輪車などが貸し出されており、乗り物の練習が出来ます。
南側地区にある白鳥の池周辺ではバードウォッチングなども出来、夏季には昆虫観察園も公開されるなど、野鳥や昆虫をはじめとした自然観察の場ともなります。
スポーツ施設としては、芝入り人工芝4面とハードコート4面のテニスコート8面、野球場1面、夏季にのみ公開されるプール(利用は小学生以下)があります。
広大な園内に張り巡らされた園路を使ったウォーキングや散歩も出来、様々な楽しみ方がある公園となっています。
休園日は毎月第1、3木曜日
荒川自然公園は、毎月第1、第3木曜日が休園日(4月のみ第2、3木曜日)となっており、祝日の場合はその日以降で土曜・日曜・祝日でない日が休園日となります。また年末年始(12月29日~1月3日)も休園となります。
開閉時間は季節・エリアによって異なります。開園は全エリア共通で、1~3月と12月が7時、4~11月が6時です。閉園は、北側・中央地区は1・2・12月が18時、3~11月が21時とな、南側地区は1・2・12月が18時、3~11月が19時となります。
最寄り駅は「荒川二丁目」停留所、駐車場は無し
荒川自然公園の最寄り駅は、都電荒川線「荒川二丁目」停留所となり、停留所がちょうど公園の南西端にあたる位置にあります。停留所から直結するような形で公園の荒川二丁目口があります。
公園北側の入口である町屋一丁目口には、都電荒川線の「荒川七丁目」停留所が最寄りとなり、入口までは徒歩3分ほどの距離となります。
バスの場合は、荒川区のコミュニティバス「さくら」の「荒川自然公園入口」バス停が、町屋一丁目口の前にあります。荒川二丁目口側のバス停は「ゆいの森あらかわ」となります。
京成本線・東京メトロ中央線の町屋駅からは、北側の町屋一丁目口まで徒歩5分ほどの距離となります。
来園者用の駐車場は用意されていません。周辺にはコインパーキングはあまり多くはありませんが、公園北側の町屋駅付近や、少し離れますが南側の荒川区役所付近には比較的多くのコインパーキングがあります。