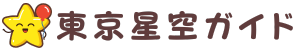冬。身体の芯まで凍えるようなよく晴れた夜、頭上高く月が煌々と輝いていたことはありませんか? 冷たく感じるほど眩しく鮮明に。
冬の月は高く明るく、夏の月は低くぼんやりしていると感じることがあります。これは感覚的なものでしょうか、それとも本当にそうなのでしょうか。
太陽の通り道「黄道」と月の通り道「白道」
月や太陽は星々の間を動いていきます。その動きをたどって見えてくる月の通り道を白道(はくどう)、太陽の通り道を黄道(こうどう)と呼びます。
白道と黄道は互いに5度ほど角度がずれていて、重なる位置が二箇所あります。日食や月食はこの位置で起こります。
ずれているとはいえ、白道と黄道はだいたい同じ高さに見えます。ということは、月が上がる高さは夏に高く、冬に低くなりそうです。太陽と同じはずですから。それなのに夏は低く、冬は高く上がります。不思議ですね。
実はこれは昼間の話。昼間の月を見上げるとたしかにこの通りです。では夜はどうでしょうか。
冬の月が高く見える理由
ここで、黄道十二星座のお話をしましょう。黄道十二星座とは、黄道が通っている十二個の星座、おひつじ座、おうし座、ふたご座、かに座、しし座、おとめ座、てんびん座、さそり座、いて座、やぎ座、みずがめ座、うお座を言います。
初めの3つが冬の星座、次の3つが春の星座、続く3つが夏の星座、最後の3つが秋の星座です。
冬の星座、おひつじ座、おうし座、ふたご座はどれも高く上がります。夏の星座、てんびん座、さそり座、いて座はどれも低いままです。
白道もだいたいこのあたりを通っていますから、夜見える月は星座と同じくらいの高さになります。つまり、冬は高く、夏は低くなるというわけです。
また月の形によっても高低は変わります。
満月は月が地球を挟んで太陽と反対側にあるときです。つまり、太陽とは反対の軌道をとるのが満月であり、冬に太陽が低く見えるのであれば、満月は高くに見えるのです。
一方で月が太陽側にある新月の状態では、冬も低い軌道を通っています。
湿度の違いも影響
この高さの違いに加えて湿度の違いが、月の見え方、くっきりかぼんやりかに効いてきます。
月を見上げるとき、月と私たちとの間には地球の大気があります。頭上に透明な毛布があるようなものですが、完全に透き通っているわけではありません。細かな塵(埃)が浮いていたり、水蒸気が含まれていたりします。埃や水蒸気には光を散らしたり吸収したりする効果があります。
さて、毛布に垂直に針を立てればすっと通るのに斜めに刺すとなかなか反対側に抜けません。通り抜ける長さが違うからです。
月の光についても同じで、高く上がっているときには大気に垂直に近い角度で入ってくるので、低いときよりも光が大気を通り抜ける距離が短く、大気中の埃や水蒸気であまり散らされることなく私たちの目まで届きます。
ですから高く上がる方がはっきり見えることになります。また、日本では冬よりも夏の方が湿度が高いのが普通です。
冬の月は湿度の低い空で高く上がります。夏の月は湿度の高い空で低空にあります。これが冬の月は高く明るく、夏の月は低くぼんやりとなる理由です。