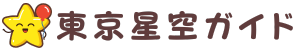国立天文台の特別公開イベント
三鷹・星と宇宙の日は、国立天文台三鷹キャンパスと、キャンパスで活動する各団体が共同で開催する年に一度の特別公開イベントです。星や宇宙に関する様々なイベントが行われます。
共催するのは、国立天文台の他、アストロバイオロジーセンター、東京大学天文学教育研究センター、総合研究大学院大学先端学術院天文科学コースとなり、日本天文学会と天文学振興財団が後援しています。
国立天文台三鷹キャンパスに加えて、隣接する東京大学天文学教育研究センターと三鷹市星と森と絵本の家でもイベントが行われます。
2020年~2023年の4年間は、オンライン開催や定員を制限した現地開催となっていましたが、2024年からは、定員を設けない形での現地開催に戻っています。
メイン講演会は3つ
メイン講演会は「系外惑星観測の始まりとアストロ・バイオロジー」をテーマとして、3つ行われます。いずれもYouTubeでライブ配信も実施されます(2つの講演はニコ生でも配信)。
東京大学天文学教育研究センターで行われる東大講演会では、東京大学の平尾優樹特任研究員を講師に、「偶然が導く冷たくて遠い惑星の見つけ方:重力マイクロレンズで探る系外惑星」をタイトルとして開催されます(11:30~12:20)。こちらは現地で午前10時から整理券が配布され、定員45名で実施ます。
三鷹キャンパスのすばる棟で行われる「国立天文台講演会」では、1回目(13:10~14:15)が前アストロバイオロジーセンター長の田村元秀氏を講師に「太陽系外惑星発見から30年、アストロバイオロジーセンター発足から10年」をタイトルとして、2回目(14:45~15:45)がアストロバイオロジーセンターの滝澤謙二特任准教授を講師に「光合成生物の系外惑星環境への適応進化」をテーマとして開催されます。現地で整理券の配布(1は12:30~、2は14:05~)され、それぞれ入替制で定員は各120名にて行われます。
複数のミニ講演会
会場内では複数のミニ講演会が開催されます。
アルマ棟会議室では、「アルマプロジェクト ミニ講演」として、6回のミニ講演が行われます。また中央棟西側では「青空天文教室」として、屋外で8回のミニ講演会が予定されています。いずれも整理券不要で参加できます。
東大天文学教育研究センターでは、「超大型観測装置見学ツアー」として、5回の見学ツアーが行われます。各回10名で整理券制で行われます。
中央棟講義室では、「太陽観測科学プロジェクト ミニ講演」として、5回のミニ講演が行われます。各回定員20名で、整理券配布により開催されます。
なお、4D2Uドームシアターでは、事前申込者限定のミニ講演会が3回行われます。
他にも様々な企画が
講演会以外にも様々なイベントが予定されています。
アルマ望遠鏡を体験するアルマ企画、すばる望遠鏡に関するサイエンスカフェやリモート観測室の見学、電波望遠鏡「SKA」の紹介、太陽望遠鏡の公開、太陽フレア望遠鏡の見学、各種のポスター展示など、三鷹キャンパス内の様々な場所で企画が組まれています。
50センチ公開展望橋にカメラを取り付けての観測や、星空ひろばに協力業者が集まっての観望会(晴天の場合は19時まで開催)など、天体観測会も行われます。
その他、最先端の天文機器の開発現場見学や、HSC銀河さがしゲーム、岡田芳朗文庫から『絵暦』に関する展示、三鷹市星と森と絵本の家で開催される「星と森と絵本の家秋まつり2025」など、様々な企画が行われます。
※写真は(c) 国立天文台